「保健体育」「スポーツ」というと、体を動かすことを主として考えられがちです。しかし、その裏には確かな知識や理論が存在しています。教育学部の臼井達矢准教授は、「スポーツ生理学」「スポーツ医学」という分野から、その知識や理論を紐解き、教育へとつなげています。今回は、臼井准教授の研究内容やこれからの保健体育に求められること、学生へ伝えていることなど、お話を伺いました。
現在の研究されているテーマを教えてください。
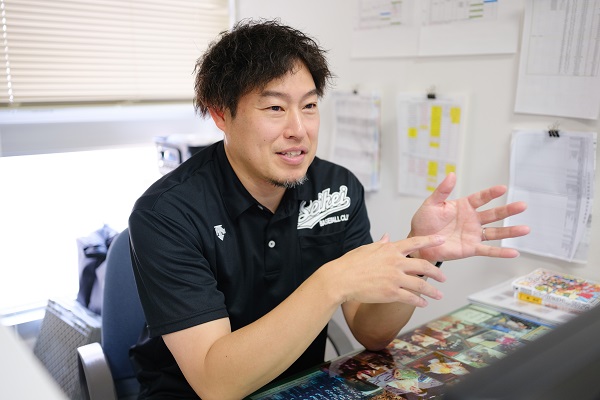
「スポーツ生理学」を専門分野として研究しています。私自身、幼少期からスポーツをしていたこともあり、少なからず怪我をしてきました。どんなことをしたら怪我をしない体づくりができるのか、今のトレーニングが本当に効果的なのかなど、高校生?大学生のあたりから考えはじめ、その興味をより深めていきたいと思ったのが、研究職を志したきっかけです。
研究職へ就くため博士課程へ進学した時に、指導教官から言われた言葉が、今でも欧洲冠军联赛の原点となっています。
「社会を揺るがす研究も大切であるが、研究を通して学生に伝え、社会に還元できる、社会と接続できる、そのような研究者になりなさい」。
当時、医学部に在籍していたのですが、中には大きな研究をしたり、新しい発見をしようとしたり、社会に多大な影響力を与える研究が広がるような世界でした。ただ、私が学ぶスポーツの世界は、そういったものではありません。スポーツの現場、社会や教育の現場に還元できるような研究が大切である。そんな研究者になりなさいと言われたことは、今でも心に刻んでいることです。
現在の研究テーマは口腔環境、口腔免疫と自律神経、ストレス、認知機能との関係性です。運動や身体活動、生活習慣や地域コミュニティに着目し、生体に与える影響を免疫学的側面や生理学的側面から解明し、特に高齢者の健康寿命延伸や、地域全体の健康増進、そして次世代を担う子どもたちの健全な発育発達に貢献するための研究と教育活動を展開しています。
一般的に体力とは、筋力や持久力などの「行動体力」といわれるものを主に捉えられていますが、私が着目している免疫力も「防衛体力」という一つの体力に分類されます。ストレスとの向き合い方や気持ちのコントロールもこの防衛体力の一部です。この防衛体力の向上が、子どもの行動体力や脳機能に好影響もたらすことも近年の研究で分かってきました。そうしたことから、学生らには授業を通じて、行動体力を高めるトレーニングや運動の重要性と共に、その根底にある免疫力、ストレスへの対処法などもしっかりと踏まえたうえで指導する必要があることを伝えています。
スポーツ(身体)を知ること、調べることは、教育とどのようなつながりがあるのでしょうか?

保健体育や部活動において身体を理解することは、自分自身の身体を大切にケアすること、些細な変化に気付くことにもつがなります。そして、パフォーマンス向上やスポーツ傷害予防、生涯にわたる健康の保持増進に貢献します。
また、知識を得たうえで実践することで、学びが深まり、理論と実践が結びついていくと考えています。例えば保健の授業の中で、循環器について説明した場合、普段の心拍数はどれくらいか、運動中にはどんなふうに上がっているかなど、自分の身体に起こっている反応を理論的と実践とを交換しながら学んでいくような保健授業ができたら、学びが深まり、興味関心も持てるのかなと思います。興味関心が持てれば自ら進んで学び、健康のために自分に合った運動を選び、行動変容につなげることもできるはずです。
さらに、子どもの発育発達という観点からから考えていくと、幼児期や小学生、中学生の時期は身体機能が大きく成長し、脳機能や免疫機能がより発達していきますが、脳にとって一番良い刺激が運動であるというのは、近年のさまざまな研究結果から分かってきています。スポーツ?運動は、子どもたちの脳を中心とした発達を底上げしてくれるものなのです。発育発達においてはスポーツをただするだけではなく、身体のことを考えて効率よく効果的に、そして安全に行うことが基本になりますから、教師は自分が体験してきたことだけでなく、科学的根拠に基づいて子どもたちへ教えることが必要になります。
加えて、スポーツは生涯にわたり、人々の健康や生活の質、満足感を高めていくために不可欠なものです。そういったことを踏まえても、スポーツの安心安全と科学的根拠が極めて重要であると考えます。科学的根拠を示すために、医学と科学から紐解く「スポーツ医科学」という分野を学ぶことも重要となってきています。
大阪成蹊大学では、どのようなことを教えているのですか?
私の担当は「生理学」という授業です。人間の身体について教えていくのですが、保健体育が学校教育になぜ必要なのかということも合わせながら、身体のことを知ることの大切さを教えています。大阪成蹊大学では生理学Ⅰ、生理学Ⅱ、スポーツ生理学、スポーツ生理学演習という4つの授業を行っています。他の教育系の大学では、1つの授業ということも少なくありません。まずは身体のことを知識としてきちんと理解したうえで、保健体育の授業につなげていく。ここに重きを置いて授業をしています。
健康を考えていくうえで、運動が大切だと理解してもらうためには、まずは「保健授業」が大事ですから、どういう運動をしたら自分の身体に良いのか、そもそも自分の身体ってどんな風にできているのだろうかという科学的な考えをすることが、これからの学校の保健体育授業には求められていくだろうと考えています。そのため、私が所属する保健体育教育コースでは、保健体育教員になるために必要な授業にプラスして、スポーツ医科学の授業を多く配置しています。そうして身体の理解をベースにした、新しい保健体育の授業づくりができる先生になれるのでは思っています。
また本学では、他大学より一足早く教育の現場を体験します。2年生の後期から1年間、小学校や中学校に行き、その後集大成として教育実習を行います。継続的に教育現場に触れながら学んでいける。現場で感じたことを大学の授業で深める。現場と大学とを往還しながら学びを充実させることができるのが大きな特徴です。
知識として得ていても、現場で実践してみると上手くいかないことは、社会人であっても多々あることだと思います。それを早い段階から経験し、上手くいくように成長できることはとても意味のあるものだと思います。ただ、学生にとっては、その分不安も大きいものです。その点は、先生方が手厚くサポートしてくれます。先生方もさまざまな専門性を持たれているので、学生も視野を広くいろんな学びが展開できます。高い専門性を持つ先生方の手厚い教育?指導が、学生の人間力の育成にもつながり、その結果として高い教員採用試験の合格率につながっているのだと思います。
高大連携イベントをはじめ、大学生とともにイベントの実施もされているとお聞きしました。

▲大阪府の高等学校で実施したスポーツ医科学連携イベントの様子
昨年度から大学生と学ぶスポーツ医科学イベントを開催しています。これまでにも高大連携授業や部活動支援として、実際に高校生に対して指導することは数多く行ってきました。さらに今回の新たな取り組みは、大学生と高校生が現代の健康課題などを解決するために、スポーツ医科学を通じて共に学び合いをするという取り組みです。具体的には、高校に訪問して、スポーツ傷害予防のテーピングやトレーニング、コンディショニング、パフォーマンスを高めるコーディネーションやリズムトレーニング、これまでのスポーツキャリアを考えるなど、多様なプログラムを行っています。高校生にとっては大学生という年齢の近い大人と関わることで将来を考える時間になり、大学生は高校生と関わることで指導力、実践力を育むことにもつながります。スポーツ医科学を通じて自分自身の身体に興味関心を持つことは、パフォーマンス向上やスポーツ傷害予防、そして生涯にわたる健康の保持増進に貢献すると考えています。
大阪成蹊大学教育学部にはどのような学生が多いですか?

人との関わりや子どもが好きな学生が多い印象です。素敵な教師に出会い、将来を志している学生が多いので、教職に対する情熱や子どもに対する愛情を持っています。また、人との関わりや協働的な活動を経験していることから、自身の強みや課題をよく理解しています。例えば、話すことは得意だけど、コツコツ勉強するのは苦手だという学生は、どうしたらコツコツ勉強できるのか、自分で考えて行動していますね。それも良い教師に出会ったからなのかと思います。学生自身も、そういった魅力的な先生になれるように。失敗も苦労も含めて、いろんなことを経験して欲しいです。
保健体育教育コースの学生には、どのような知識?スキルを身につけて欲しいですか?

保健体育科の専門性と実践力を身に付けながら、複雑な現代社会のニーズに対応できる力を身に付けて欲しいと思います。具体的には、科学的根拠に基づいた指導力、健康に関する幅広く深い多角的な知識、情報活用能力(ICT活用)を踏まえた個別最適化された指導力、変化や社会ニーズに対応する柔軟性と探究心、地域連携など社会に開かれた教育視点とアウトリーチなど。そのためにも、大学でいろんな方に触れ、さまざまな知識を得て欲しいと思います。
「保健体育」というのは、言葉の通り保健が先。何をするにも人の健康があってこそのものです。身体だけでなく、心の健康も大切です。自分以外の外(社会)とつながっているか、自分の居場所があるかなどが、心の健康につながります。スポーツは、人と人とのつながりを深める、コミュニケーションツールにもなるものです。運動しながらスポーツを通して会話をしたり、自分の居場所が感じられるようになる。そして、身体も心も健康になっていく。そのような視点で、保健体育教師は単なる「体育の先生」という枠を超え、児童生徒の心身の健康と成長を包括的にサポートする「ウェルネスの専門家」としての使命を持って学んで欲しいと思います。
最後に、教育に関心を持つ学生にメッセージをお願いします。

教育は人なり。人に関わる仕事(先生と呼ばれる仕事)であるからこそ、自分自身はさまざまな経験をし、学び、成長し続けることが重要です。自分自身を高められない教師は、子どもたちも高めることができないと思います。 教育の分野に興味関心を持つ高校生の皆さんには、まずは今の高校生活を大切に、そして自分自身の強みと課題を理解し、自分自身の成長に努めてください。人に教えることを学ぶ前に、自分自身に対してどうあるべきか、どうすべきか、どのような考えで取り組むべきか、どのような成功や失敗があるのか、ぜひトライ&エラーを通じて、大いに高校生活を充実させてください。そのきっかけに本コースが取り組む大学生と学ぶスポーツ医科学イベントも役立つと思います。
<大阪成蹊大学 教育学部 教育学科 中等教育専攻 保健体育教育コースの学び>
/department/education/health-physical/



.jpg)